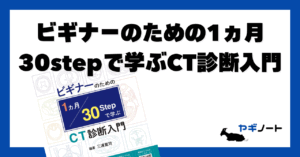この記事は約5分で読めます
【書評】「X発!10秒で読める画像診断」は買いか?専攻医3年目の率直レビュー
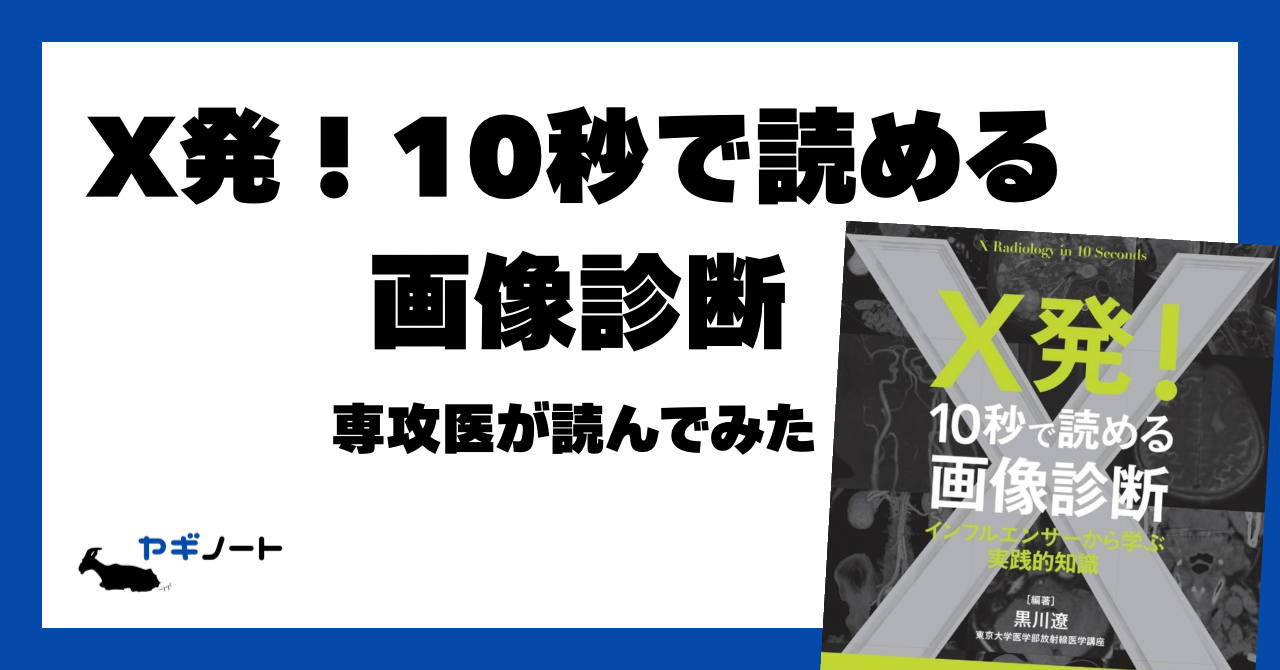
こんにちは、やぎ(@yagi_note01)です!
X(旧Twitter)で画像診断を勉強している人なら、#Rdiagというハッシュタグを見たことがあるのではないでしょうか。
画像診断関連の情報について有志の先生方がまとめてくれているハッシュタグであり、読むだけで非常に勉強になります。
放射線科専攻医として#Rdiagの投稿を追いかけていましたが、いいねやブックマークをしても、なかなか見返すことがありませんでした。そんなときに出会ったのが、この本です。
「X発!10秒で読める画像診断 インフルエンサーから学ぶ実践的知識」は、X上の投稿を体系的にまとめた、初の「X発の画像診断本」です。
著者の黒川遼先生(@Rdiag2)をはじめとする画像診断のインフルエンサーたちの投稿が、201症例・5つの章に整理されています。
この記事では、放射線科専攻医3年目の私が実際に本書を読んでみた感想と、日常診療での活用法を紹介します。
X上で#Rdiagを追いかけている人、日常の読影業務で知識を増やしたい人の参考になれば幸いです。
本書の特徴:X上の投稿が一冊に
本書の最大の特徴は、タイトル通り「10秒で読める」手軽さです。
1症例が1ページにまとまっており、タイトルと画像を見るだけなら10秒、全体を読んでも1分で完結します。解説も140字以内とコンパクトで、X上の投稿フォーマットがそのまま活かされています。
全201症例は、以下の5つの章に分かれています。
- Part 1:診断一般(90症例)
- Part 2:Aunt Minnie(一発診断)(35症例)
- Part 3:鑑別リスト(8症例)
- Part 4:治療関連変化(29症例)
- Part 5:ピットフォール(38症例)
特にPart 1が充実しており、全身のさまざまな部位・疾患について学べます。
X上で流れていく投稿が体系的にまとまっているのが最大の魅力です。いいねしても見返さない問題が、この本で解決しました。
従来の画像診断の教科書は、分厚く体系的に学ぶスタイルが主流でした。
辞書的に使うのには向いていますが、忙しい日々のなか通読するのは正直にいって困難です。
それに対して本書は、オムニバス形式でさまざまな疾患がどんどん紹介されていきます。体系的ではありませんが、通勤時間や読影の合間など、隙間時間で読めるのが最大の強みです。
実際に読んでみた感想:良かった点
日常診療では、指導医からTipsやクリニカルパール、読影のコツなどを教えてもらうことがあります。
こうした口伝で伝えられた知識は、記憶に残りやすいと感じています。
読影レポート作成時に「そういえば、こんなことを聞いたことがあるな」とふと思い出すことがあります。
本書の内容は、まさにそういった指導医からの一言をまとめたようなイメージです。
1症例が簡潔にまとまっているため、分厚い教科書の詳細な記述よりも、かえって記憶に残りやすい気がします。
実際に、読影レポート作成時に本書で読んだ内容が日常診療のなかでリフレインされる感覚がありました。
特にPart 1(診断一般)は90症例と最も充実しており、全身のさまざまな部位・疾患について学べます。
中枢神経系から筋骨格系まで幅広くカバーされており、知らなかった疾患や所見も多くありました。様々な切り口で書かれているため、飽きずに読み進められます。
また、X上で#Rdiagの投稿を見たことがある人にとっては、良い復習の機会になります。
「これ、Xで見たことがある」という症例も多く、流れていった投稿を改めて定着させることができました。
読影中に「あれ、これどこかで見たな」と思い出せる瞬間が増えました。日常診療で役立つ知識のストックとして優秀です。
通勤時間に1-2症例ずつ読むペースがちょうどよく、無理なく続けられます。
分厚い教科書を開くのは心理的ハードルが高いですが、この本なら気軽に手に取れます。
この本が合う人・合わない人
本書が合う人・合わない人を整理してみました。 こんな人におすすめ こんな人には向かない X上で#Rdiagを追いかけている人 初期研修医(基礎知識が前提) 日常の読影業務で知識を増やしたい専攻医 読影法を一から体系的に学びたい人 Aunt Minnie的な知識を増やしたい人 専門医試験対策だけが目的の人 隙間時間で勉強したい人 放射線科志望の研修医
本書は、X上で#Rdiagの投稿を追いかけている人には特におすすめです。
日常の読影業務で知識を増やしたい専攻医、Aunt Minnie的な知識を効率的に増やしたい人、隙間時間で勉強したい人に向いています。放射線科志望の研修医にも良いでしょう。
一方で、初期研修医には不向きです。
基礎的な読影スキルがある前提で書かれているため、画像診断に馴染みがない段階ではイメージが湧きにくく、難しいと感じるでしょう。
また、オムニバス形式で体系的ではないため、読影法を一から学びたい人には向きません。
専門医試験対策としては、試験に直結する内容ばかりではないと思います。
あくまで日常診療で役立つ実践的知識がメインなので、試験対策だけが目的なら他の参考書と併用する方が良いでしょう。
基礎的な読影スキルがある前提の本です。初学者には難しいですが、ある程度経験がある人なら確実に楽しめます。
他の教科書との使い分け
画像診断を学ぶには、まず基礎的な教科書で体系的に読影法を学ぶことが重要です。
基礎を固めた上で、本書のようなオムニバス形式の本を読むことで、知識の幅を広げることができます。
本書の位置づけは、基礎習得後の「知識の幅を広げる」段階と考えます。
日常診療で遭遇するさまざまな疾患について、Aunt Minnie的な知識を効率的に増やせます。体系的な教科書と併用することで、より実践的な力がつくでしょう。
私は電車での通勤時間に1-2症例ずつ読むようにしていました。無理なく続けられるペースが大事です。
私の活用法:Obsidianでの運用
個人的には、本書の内容をObsidianでマークダウンファイル化して運用しています。
各症例を個別のページにすることで、他の医学知識とのリンクを構築しやすくなります。Obsidianの双方向リンク機能を使うことで、関連する疾患や画像所見を横断的に参照できるのが強みです。
[ここにObsidianのグラフビュー画像を挿入]
具体的な手順については別記事にまとめる予定ですが、Obsidianの双方向リンク機能により、医学書の知識を体系的に管理できるのが大きなメリットです。
おわりに
「X発!10秒で読める画像診断」は、手軽さと実践性が最大の魅力です。
「指導医からの一言」のように簡潔にまとまった知識は記憶に残りやすく、読影レポート作成時にふと思い出せる実践的な知識として役立ちます。
X上で#Rdiagの投稿を追いかけている人、日常の読影業務で知識を増やしたい専攻医には特におすすめです。
一方で、基礎的な読影スキルがある前提の本なので、初学者には不向きです。基礎を固めた上で、知識の幅を広げる段階で読むと最も効果的でしょう。
私自身、放射線科専攻医として本書を読んで、日常診療で役立つ知識のストックが増えたと実感しています。
この記事が役に立てば幸いです。それでは。
[Amazonアフィリエイトリンク]
よかったらシェアしてね!